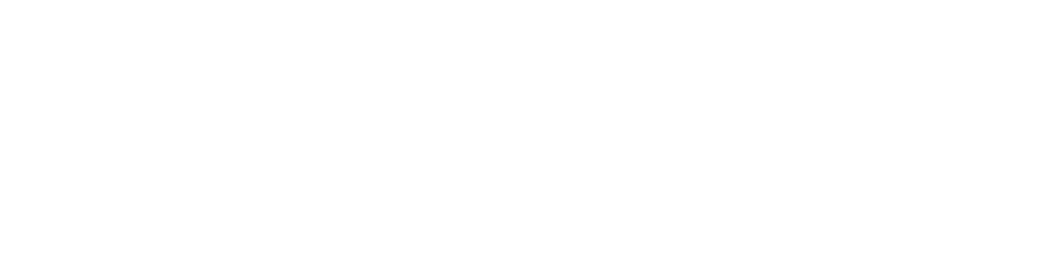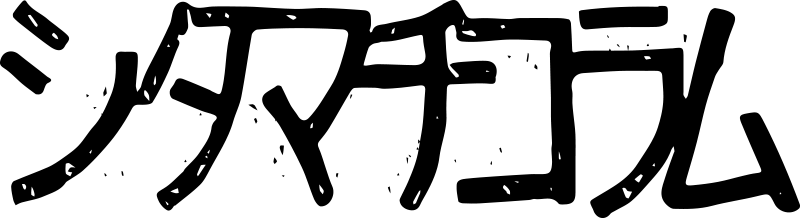筆者:くりのさやか(下町ぐらし研究所)
編集:岩本順平(DOR)
イラスト:六一
こんにちは!下町ぐらし研究所のくりのさやかです。3部作コラムの最終回をお届けします。今回は、何気ない下町の日常を研究者の方々と掘り下げたイベント「下町アカデミック」のレポートをお届けします。
このイベントを企画したきっかけは、私たちが感じる「なんだか心地いいな」という感覚って、もしかしたらすごく社会的に大切なことなんじゃないか、これを研究者の方なら言語化できるんじゃないか、という仮説を思いついたからです。
その仮説を実証していくために、社会学や教育学などの研究者の方々をお招きしトークセッションを実施しました。当日、会場のふたば学舎には約80名の方が集まり、大盛況!当日のレポートをお楽しみください。
セッション①DIY精神で社会をつくる!

1つ目のセッションでは、社会学者の松村淳さんと文化人類学者の早川公さんが、長田の持つ「チャレンジする土壌」について語ってくれました。
松村さんは「長田には適度な『隙間』や『余白』がある」と言います。「最近、コミュニティを語る際のキーワードとして、余白とか隙間とか境界という言葉を聞きませんか。それは本能的に多くの人が社会の中での余白みたいなものを求めてるんじゃないかなと思っていて。そういった意味で、長田はいい感じに余白があるので、いろんな人が入ってこれやすいということですよね」
早川さんは「まぜこぜ」という言葉で長田を表現しました。
「いろんなものがまぜこぜにあるっていうのもポイントなんじゃないか。例えば、(進行役の)まいさんもいろんなことやっていて、何してるかわからない人じゃないですか。なぜこれを変だと思うかというと、今の世の中は基本的に仕事や職業は1つだけで、それ以外のことはしていない。お店に関しても、これはカフェですとか、これは宿泊業ですみたいな形で、(役割を)1つ1つ分けていくことを良い価値観だと思って生きている。そういう感覚でここに来ると、ダンサーが本業ではないけれど踊っているというような「この人は何してるかよくわからない人」がいる。そういった生き方として、いろんなことをまぜこぜにしているのが大事なんじゃないかな」
第1部でファシリテーターを務めていたいた小笠原舞さんは2人の話を受けて、「このまちって「ないならやればない」みたいな、結構そういう人が多くて。「あ、じゃあなんか手伝う」みたいなそういう空気もすごく当たり前なので。そのDIY精神でいろんな「ないなら作っちゃえ」みたいなのが気軽。」
「チャレンジする土壌」をテーマに語っていただく第1部は「余白」や「まぜこぜ」、「DIY精神」といった言葉ができて幕を閉じました。下町にあるこれらの要素が、チャレンジする人が増えていく要素なのかもしれません。私たちが無意識に感じていたことが言葉になっていっています。
セッション②下町からみるライフスタイルの可能性

2つ目のセッションでは、社会学者の轡田竜蔵(くつわだ・りゅうぞう)さんと家族社会学者の永田夏来さんが、下町ならではの働き方や家族のあり方について考察してくれました。
轡田さんは「『面識経済』という概念は顔の見える関係の中だけで生活できることが幸せという話で。興味深いのは、この『面識経済』のキーワードになるのが『隙間』なんですよね。(前のセッションで)松村さんも「余白」という言葉を使っていましたが、同じような概念です。ギュッと集中したまちより、むしろスカスカな状態の方が外から来た人も入りやすく、自由にやっていいと感じるという。だから実は田舎や下町の方が、今の時代はクリエイティブなことができる余地があるのではないでしょうか」
永田さんは「リミナル(境界の曖昧さ)」という概念で下町を表現しました。「長田の魅力は、みんながよく知っている言葉で言うと「カオス」や「混沌」のようなものだと思っています。もう少し専門的に言うと「公私の曖昧さ」です。パブリックとプライベートの境目が曖昧で、そこをはっきり線引きしない。この「公私の曖昧さ」を私は「リミナリティ」と呼んでいます。長田のリミナリティは、おそらく震災体験が関係していると思います。災害などカオスな状態を共通体験した人たちの間では繋がりが強くなります。震災をみんながくぐり抜けて、なんとか頑張ってきたという共通体験があって、それが今の暮らしやコミュニティを支えてて、チャレンジも支えてくれているのかなと思います。」
このセッションには東京から移住して1年の織戸祐三子さんも登壇しました。織戸さんはちょうど今、このまちで子どもや大人が創作活動をする場所「ナガタbond(ボンド)」を立ち上げようとしています。
「東京でも似たような創作の場を作ろうと試みたんですが、続きませんでした。でも長田に来たら、暮らしと仕事がみんな近い形で過ごしている人がたくさんいて、私も会社勤めで長田から通勤するよりは、近くで自分ができることをやってみたいと思いました。身近に相談できる人がすごくたくさんいるので、ここなら小さく始めることにチャレンジしてみようかなと思いました。」
このトークセッションの進行は私が担当したのですが、トークセッションから「チャレンジという言葉にグラデーションがある」と感じました。「チャレンジ」や「起業」というとハードルが高いように感じますが、このまちの人々を見てみると、友人たちと作ったものを販売するイベントをやってみるとか、下町ぐらし研究所の部活動でも中高生たちが畑をやっていたりして、チャレンジにはグラデーションがあるなと感じます。サポート体制も、一緒になってイベントを作ったり、助成金の申請書を一緒に作ったり、やりたいという気持ちや困りごとを聞いて応援したりと様々な形があるように思います。それは行政が特別に何かをしているというよりも、まちの人同士で何かしらサポートし合っているものが多いのではないかと感じます。」
『下町からみるライフスタイル』ということで働き方やチャレンジについて語り合った第2部からは、『面識経済』や『リミナリティ』という新たな視点が生まれました。下町では公私の境界が曖昧であり、チャレンジにも大小様々な形があることが見えてきています。まちの人々が自然とサポートし合うこの土壌が、新しい何かを生み出す力になっているのでしょう。
セッション③子どもの言葉から考察する、まちでの学びの可能性!

最後のセッションでは、教育社会学者の粕谷圭佑さんと教育実践者の下向依梨(しもむかい・えり)さんが、長田での子どもの育つ環境について語ってくれました。
粕谷さんは「公共空間では基本的に知らない人に話しかけない、というのが一般的だけど、下町の喫茶店では子どもが常連客に絵を見せるという場面がある。大人が同じことをしたら違和感があるでしょうが、子どもだからこそ自然に受け入れられる。そういった(子どもたちを自然に受け入れようとする)文化がこのまちにはあるのかなと。」
下向さんは「このまちには「キュレーター」のような存在がいる」ということに注目しました。「誰々さんはこれが好きなんじゃない?」とか、「あの人が助けてくれるはず」というように、人を繋ぐ声かけをする人がいます。子どもたちにも同じように声掛けしているなと思っていて、一人ひとりに合った場所が見つかり、自己有用感や自己肯定感が高まっていくと思います。」
進行の今井さんはゲスト二人の話から「(ゲスト二人が話した「子どもが自然に受け入れられる文化」や自己有用感や自己肯定感が高まるような人の声掛けから)子どもなど弱い立場の人たちが健やかに生きられる場になるのだろうなと。そうすれば、子どもだけでなく大人たちも健やかに生きられると思います。皆さんが幸せに生きていくことに直結していると思いながら取り組みを続けていきたいです。」と語っていたのが印象的でした。
教育について語り合った最終セッションからは、『公共空間での自然な交流』や『キュレーターという人を繋ぐ役割』といった視点が浮かび上がりました。子どもが常連客に絵を見せるような何気ない場面や、一人ひとりに合った場所を見つける声かけが、このまちの日常には当たり前にあります。こうした環境が子どもだけでなく、すべての人の健やかな暮らしに繋がっていくという気づきは、下町の持つ豊かさの本質を表ているのかもしれません。
研究という「眼鏡」を通して見えたこと

3つのセッションを通して、私たちの「なんとなく良い」と感じていたことが、学術的にも価値あるものだと再認識する機会となりました。研究者の言葉は、私たちが日常で感じていることに「名前」を与えてくれました。一見すると古いまち並みの中に、実は移住促進や地域の活性化、少子高齢化社会における教育など現代の最先端の課題を解決するヒントが隠れているのかもしれません。
さて、3回にわたって長田での暮らしや活動について綴ってきました。移住者として感じた「生きやすさ」から始まり、「下町ぐらし研究所」の活動を経て、未来に向けた下町に眠っている価値まで。
「下町アカデミック」を通して強く感じたのは、私たちが何気なく過ごしている日常が、実はとても貴重なものだということ。そして、それは決して過去の遺物ではなく、むしろこれからの社会にとって大切な価値を持っているということ。それを伝えていきたい、そんな思いを新たにした1日でした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
私たち下町ぐらし研究所の活動に興味を持ってくださった方は、ぜひinstagramをみて遊びにきてくださいね!

くりのさやか|下町ぐらし研究所事務局
1995年、新潟県生まれ。大学進学と共に上京し、社会人としてのキャリアを積んだ後、2021年に神戸へ移住。多様なNPOや地域団体との関わりを通じて、ソーシャルスタートアップの要となる「事務局チーム」の魅力と、その担い手育成の重要性を探求している。
かつては情熱のままに走り、ボランティア活動に私生活のほとんどを捧げた結果、バーンアウトを経験。今は、自分の情熱を追求しながらも、日々の暮らしに余白を持ち、自分自身を大切にする生き方を模索している。
Twitter:https://x.com/8989manpuku
note:https://note.com/kurichandaze
Instagram:@corocorowarae
下町ぐらし研究所:@shitamachigurashi.lab
掲載日 : 2025.04.29