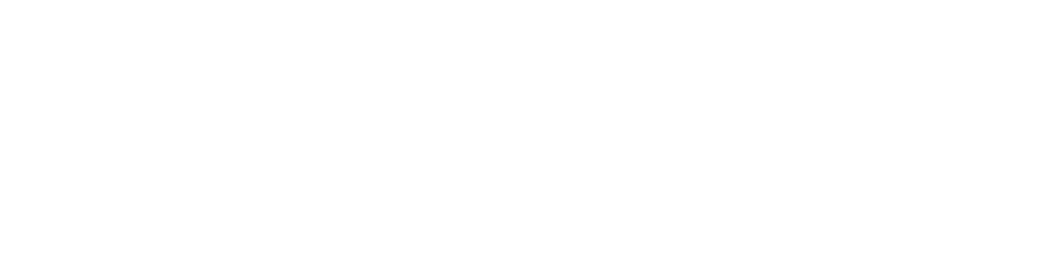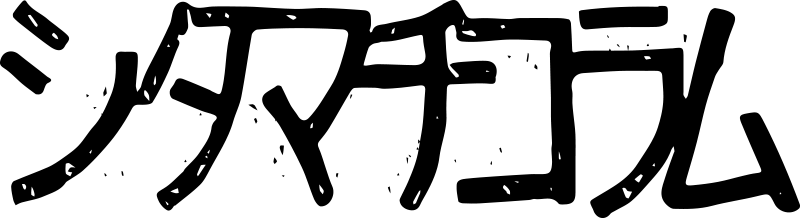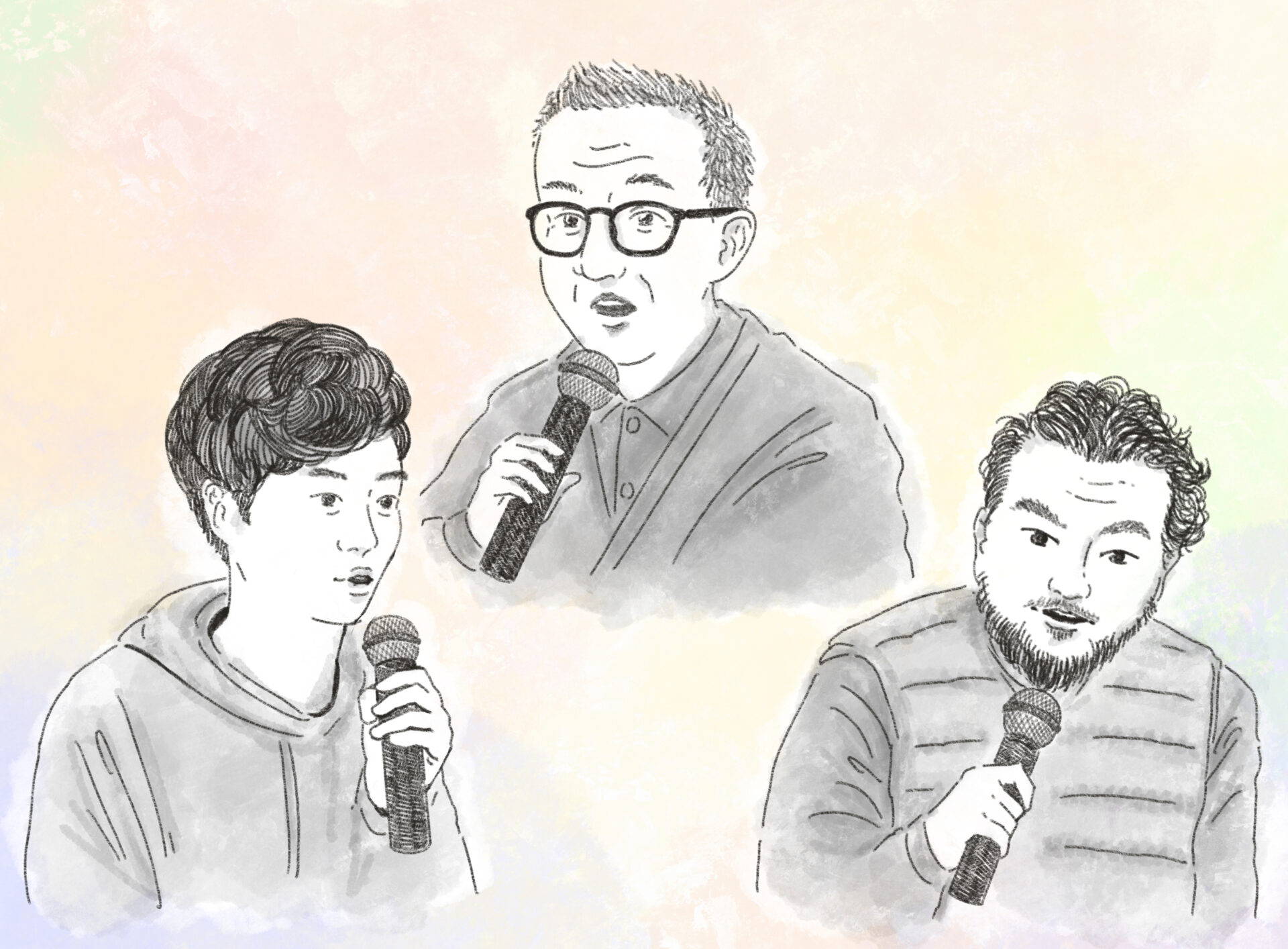
文:竹内厚
2025年1月26日、約5時間におよぶ全4部のシンポジウムが開催。10人以上の登壇者が順々にステージに上がり、その合間にはいくつかのパフォーマンスも披露されるという出し惜しみない内容で、最初から最後まで見届けた観客も数多く、終幕も驚くような形で演出されました。
そもそも「30年後の情景PROJECT」とは、烏原立ヶ畑堰堤、旧駒ヶ林公会堂、兵庫津、六甲山に新長田の下町を結ぶようにして、ユニバーサルツーリズムの実現を目指すというもので、新長田に拠点を構える株式会社Happyが主催。2024年度の文化庁の助成を受けて、震災30年となるこの2025年にスタートを切りました。
Happy代表でカオスクリエイターを名乗る首藤義敬さんの呼びかけで始まったシンポジウムは、いろんな文脈の話が入り混じっていたため、全4部を順に振り返ってもむしろ煩雑になるだけかも。ということで、勝手ながらこちらでテーマを3つに絞って、その日に話されたことや感じたことなどをまとめます。第1回は「30年という時間のこと」。
なお、筆者の私は大阪に暮らしていて、事務所はデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)にあるので完全なよそ者というわけではないですが、神戸に根差した地元民ではありません。
シンポジウムの第1部は「これまでの30年を振り返る」がテーマに。阪神・淡路大震災から30年を迎えた2025年、神戸の各地で30年を機とした行事やイベントが開かれ、多くのメディアが震災30年にまつわる取材記事を発信、関連企画を催す施設も山ほどあります。私も震災30年関連の取材に関わる機会がすでに結構あり、といって、そこで聞かれる個人の声は本当に多様でデリケートで、30年だからといっての浮ついた気分というのは皆無でした。ただ、イベント開催やメディア発信という形になると、個々の内実に関係なく、ただ「震災30年」という言葉だけがひとり歩きしているという印象を持つ人もいるでしょう。
そんな中、本プロジェクトも30年を謳っているわけですが、そのあたりの理由について首藤さんはこのように言っていました。「ぶっちゃけ僕、この街は結構苦手やったんです。でも、あれから30年経って、あの頃のまちの先輩方の年齢って今の僕らと一緒やんって気づいたんです。このまちの復興についてもっとちゃんとしてほしかった…とか、ずっと文句ばっかり言ってきたけど、とはいえ、あれだけ何もかもなくなってしまった新長田の状況から、ここまでの街ができてるやんって。僕もやっと30年経ってこういう話ができるようになってきた。すごく大事なことって時間がかかるし、なんかわかりにくいし、でも意外とシンプルやなって思ってます」。
震災30年ということでいえば、映画『港に灯がともる』の監督・脚本を務めた安達もじりさんも第1部に登壇。オール神戸ロケで撮影された震災後の神戸を描いた映画は、事前の膨大なリサーチがうかがえるものでしたが、その制作について、「震災からの30年って一体何だったのか。そのことについて立ち止まって考えないことにはこの映画を作り始めることはできませんでした」という安達もじりさんもまた、30年という時間に向き合ってきたひとりといえます。
そして、第1部に登壇したもう一人、本サイト「シタマチコウベ」を運営する写真家の岩本順平さんは、震災時は3歳、神戸外に暮らしていたそう。「新長田に移ってきて、実際に震災に直面した方たちとプロジェクトを進めるときにすごく配慮というか、自分は当事者じゃないという難しさを感じていたし、新長田が被災地じゃなくて普通の街としてやっていけたらと思っていろんなプロジェクトをやってきたので、正直、あえて30年に映画を作る理由って何だろうと思ってたんです、実際に映画を見るまでは」と映画に絡めて、この街で過ごしてきた実感に触れました。
映画『港に灯がともる』が描く、街と家族と個人の大変すぎる状況は、とてもリアルであるだけになかなか公には口にするのもためらわれるようなこと。それを半端に夢物語にされても反感がつのるばかりですし、といって真正面から挑んで映画として着地させられるのか…映画を見るまでは不安要素しかなかったというのは、岩本さんに限らず、神戸の街で活動を続けてきて、そのデリケートさを肌身に知る人ほど感じていたことかもしれません。
実際に映画を観ると肯定的な感想を持ったという岩本さんは、今回のプロジェクトにつなげるようにこれからの30年についてこう話しました。「復興や再開発とかって大きな話になりがちで、けど、この映画のように個人の営みにフォーカスを当てることが大切で。これまでとこれからの30年を考えるという点では決して何かを否定するのではなくて、なるべくニュートラルに捉えたいなと今は考えています」。
30年というのはひと世代が移りゆくような時間間隔でいましたが、第2部で登壇した木材コーディネーターの山崎正夫さんによれば、植樹から伐採まで60年ほどかかる林業の感覚でいえば、30年というスパンはとても短いのだそう。「ひと世代では継げない、孫のために木を植える」のが林業だと。
シンポジウムを通じていろんな30年の捉え方を聞くなかで、映画の制作にのぞむ気持ちを振り返って話してくれた安達もじりさんの言葉をもうひとつ記録しておきます。「30年後の情景PROJECT」へのメッセージのようにも聞こえましたので。
「いろんな方にお話を聞いてみると、30年という時間の長さ、短さというのは本当に人それぞれで受け止め方が違っていると感じました。その誰の気持も否定したくないというような思いで、いろんな人の思いを紡いでいけば何が起きるんだろうという感じで映画を作っていきましたし、この時間はこれからも続いていくわけなので、ほんの半歩でも希望をもって前へ進めていけたらいいのかなって」。
なお、「30年後の情景PROJECT」では、30年間、毎年こうした機会を何かしら持ち続けたいとのことです。
※発言はすべて「30年後の情景PROJECT」の「文化財のある地域の未来を考えるシンポジウム」(2025年1月26日開催)での発言をもとにしています。
掲載日 : 2025.02.22